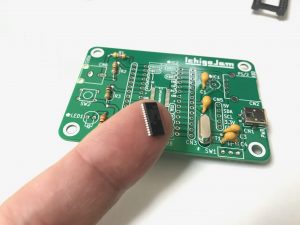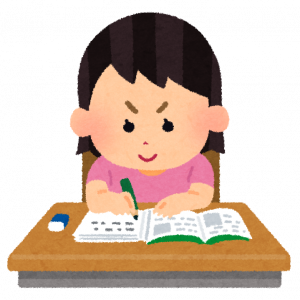今日本当にあった話。
学生時代からのツレの一人が今いる現場はセキュリティが厳しくて、私物携帯の持ち込みが制限されている。彼がその現場にいるタイミングで80歳オーバーのお母さんさんのPCのメーラが起動しなくなる。お母さんはメールができないので、息子の携帯に電話する。すると「圏外です」と言われる。お母さん焦る、お父さんに言う、お父さん、電話やメールしてみるが、返事がない。もう、もともとのお母さんの話題は飛んでしまって、息子大丈夫か?の方が問題になってしまう。昔、息子から知らされたツレの携帯に電話かける、連絡先のひとつだった番号はオレの前職の番号w。
電話を受けた後任者がヤバいと思ってオレにメッセージしてくる、みたいな連鎖。だって、やたら心配したお父さんからの電話だからな。オレと思ってその番号に電話かかって来る時ってだいたい悪い知らせだという実績もあり。そのタイミングではお母さんの命に関わる重大事かも?的なニュアンス。おい、あいつ、息してるか?twitterの投稿は19時間前。まじか。仲間総動員して連絡する。あっさりつながる。えっ?
お母さん、PC再起動で復旧。
それはそれでよかったし、お父さんお母さんには罪はないし、むしろ心配するのは当然のこと。
しかし、探される身や連絡を受ける身としてみると、こんなアラートで神経すりへらしたくない。
とわいえ、明日は我が身。実家の両親へ適切な連絡先とプライオリティを告知しておかないといけないな、と感じた次第。
携帯やら連絡手段が確立された今、ちょっとでも連絡がとれない時の騒ぎ方がちょっと過剰かなとも思う。
そして、認知症ぎみな老人達のアラートの上げ方の雑さがアレ。

IT全般・情シス・モバイル端末・ラーメン・ランニング・旧いクルマ・ネコ自慢などをつぶやくフツーの爺さんです。主食は焼き鳥、餃子は飲み物。インターネット老人会。クルマ無し生活3年目。Threadsで日々のつぶやきは書いてますので、興味のある方は@ryoshrをフォローしてください。blogの記事に対するコメントは、即時反映されませんので、ご注意ください。人力モデレートです。
whoami : http://about.me/ryoshr
Threads:@ryoshr
X : @ryoshr
facebook : @ryoshr
Instagram : @ryoshr